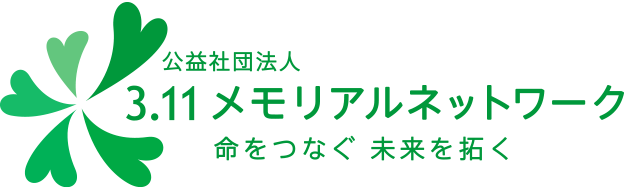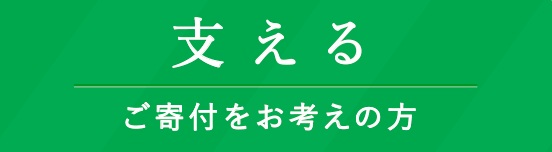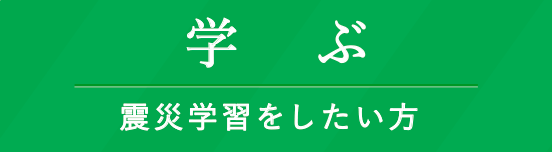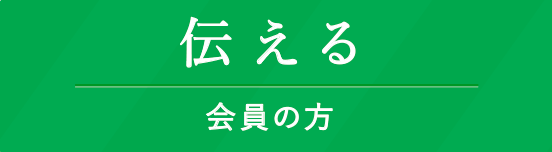【第8回】明日が来ることは「奇跡」命がけで伝える

「会員インタビュー」連載第8回目のゲストは、宮城県石巻市出身・塩釜市在住の髙橋匡美さんです。
2015年3月から語り部の活動を始め、英語での語り部にも取り組まれています。実は、インタビュアーの藤間と髙橋さんは、2015年当時から二人三脚で語り部に取り組んできた仲。今回は改めて、髙橋さんの故郷の思い出から、語りを始めたきっかけ、現在の活動や思いを伺いました。
なお、今回も、新型コロナウイルス感染対策でマスクを着用してインタビューを実施しています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
《この記事は約8分で読めます。》
髙橋 匡美(たかはし きょうみ)
宮城県石巻市出身・塩釜市在住
石巻市南浜地区で生まれ育つ。3.11当日は塩釜市の自宅で被災した。地震発生から3日後、南浜町の実家を目指して移動するが、故郷の街は津波で失われ、最愛の両親は津波で犠牲になった。2014年にスピーチコンテストに出場し全国大会で受賞したことをきっかけに、体験を語りはじめ、今も”命のかたりべ”として活動している。英語での語りにも挑戦し、海外の方に向けた講話も実践している。2017年から、かたりべに死生学の授業を織り交ぜた金菱清教授 (関西学院大学)とのオリジナルの講演、「疑似喪失体験プログラム」も手掛けている。
地元・石巻市南浜町の思い出
匡美さんは生まれてからずっと南浜なんですよね。
髙橋さん) はい。生まれてすぐは2丁目の小さな借家で暮らし、その後4丁目の父の会社の社宅に入り、小5の時に2丁目に家を建てて引っ越したんです。平日の上棟式だったけれど、小学校の先生が「一生に一度の機会だから帰りなさい」って言ってくれて、学校を早退して参加しました(笑)父が誇らしげに餅をまいていたのを覚えています。
そんなことをしてくれる先生もいたんですね。
髙橋さん) 当時、私の家の周りは野原で、木造の空き家を友だちと探検したりしました。その後に宅地開発が進みました。
少しずつ大きくなっていく町を見ながら成長されたんですね。


東日本大震災前の石巻市南浜・門脇地区の一部。左上が日和大橋、右上が市立病院。
海のそばで暮らす中で、災害で怖い思いをされたことはありましたか?
髙橋さん) ベランダから堤防が見えるような場所だったので、台風が来たりすると家からも白波が見えていましたね。
あと、働き始めたばかりの23、24歳くらいの頃、仕事を終えて車で走っていたら、地面に水がサーッと流れてくるのが見えて「なんだろうこれは」と思いながら家に帰ったのですが、父と母に言ったら「それは高潮だ」と。
似た話を聞いたことがあります。土のう袋を積んで備えている時に、高潮で仲間が流されたとか。
髙橋さん) 危機感がないうちに、サーッとくるんですよね。消波ブロックを埋めてから高潮による浸水は無くなったと聞きますが、私の記憶では、南浜で高潮を2回経験していて、低い土地の家は床下浸水もしていました。
夜寝るときに波の音が聞こえていても「そんなもんだ」と思っていて、そこまで海に近いという認識はなかったんですよね。
お母さんの日記
髙橋さん) 高校卒業後は、1年間仙台で音楽教室の先生の資格を取るための勉強をしてから、石巻に戻って来ました。「こんな田舎に居たくない」と、東京とかに出て行く友人も多かったですけどね。
匡美さんは地元が好きだったんですね。
髙橋さん) そうですね。近くにスーパーもあるし、服は母が縫ってくれたし、自転車で行ける距離で完結していましたし、出たいと思ったことは全然ないです。結婚して家を出る時に、「さみしい」「お母さんのそばを離れるのが嫌だ―」って泣いたくらいです(笑)
かわいいです(笑)

髙橋さん) 母は「さみしい」なんて全然言わなかったんです。ところが、亡くなって母の日記が出てきたときに、「さみしい」という言葉ばかりでびっくりしました。
日記に本当の気持ちを書かれていたんですね。
髙橋さん) 直接言ってくれたらいいのにね(笑)一番最後に書かれた日記が2011年3月4日だったんです。本当に年とったなとか、お父さんも文句言ってるけどとりあえず元気だし、孫に会いに行こうとか書いてあって、「私は今のところとっても幸せなのだ」で終わっているの。このメッセージを私たちに残していくなんて潔いと思いましたね。
かっこいいですね。語り部でのお話を聞いていても、匡美さんのお母さんって勢いがありますよね。南浜は、匡美さんをつくった場所ですね。
髙橋さん) そうですね。うちの母が一番活動していた場所なので。
3月11日
3月11日の地震が起こった時は、何をされていましたか?
髙橋さん) その日は13時で仕事が終わって、塩釜の自宅に帰ってきていました。15時に歯医者の予約があって、「さて、出かけようかな」という時に地震が起こりました。
揺れはかなり長かったわけですが、その間に考えたことや行動したことを覚えていますか?
髙橋さん) 「実家に電話しなくちゃ」とは思いましたね。10年以内に90%以上の確率で”宮城県沖地震”が来ると言われていて、それがきたのかと。初めは「この程度で終わるなら、いいか!」と思ったのですが、揺れは長く続いて、耐震性の扉の食器棚も中身が落ちて、しっちゃかめっちゃかになりました。

髙橋さん) 防災無線から「津波が来る」と聞こえました。2匹猫を飼ってるのですが、1匹は揺れで開いた戸から二軒隣のベランダに逃げて、もう一匹は息子の部屋のベッドの下に隠れていました。
息子さんや旦那さんとは、いつ合流で来たんですか?
髙橋さん) 息子は夜中の12時くらいに帰ってきました。夫は、14日の夜に連絡が来ました。主人は当時ホテルで働いていて、お客様を避難させるのに必死だったようです。
石巻へ
髙橋さん) 家に帰ってきた息子と、11日の夜中に石巻に行こうとしたのですが、タイヤがパンクしてしまったんです。
12日にはパンクしたタイヤを付け替えたり、ラジオとか電池を探したり、色々やっているうちにまた真っ暗になって、ラジオを聞きながら寝ました。そのラジオで「公衆電話が無料で使えるようになった」とか「荒浜で200、300のご遺体が見つかった」といった情報を耳にしましたが、石巻の情報はなく、「じゃあ大丈夫なんだろうな」と思っていました。

髙橋さん) 13日には、塩釜市内で情報収集をして歩きました。公民館に行ったらテレビがあって、「私は今、石巻にいます!公民館にバスが乗っています!」という音声が聞こえて、その時、やっと危機感に目覚めました。尋常じゃない声とか、ヘリコプターの音で、想像以上の事が起きていると。そして、14日の朝から、息子と一緒に石巻に向かいました。
途中から、車では進めなくなって歩いた、というお話をきいたことがあります。
髙橋さん) そう。道中、根っこから抜けてる大きな松の木がとてもたくさんあって、「なんだろうな」と思っていました。なんでこんなに木があるのか、分かっていなかったんです。日和山から降りてきて、バーっと視界が開けたときに、「なんだこれは」と。低空飛行するヘリコプターと、暑さと、焦げ臭さと。ガタガタと震えて、膝から崩れ落ちそうになって、言葉を失うとはこういうことだなと思いました。目の前の現実を受け止めきれないけど、受け止めざるを得ない。そういう感じでした。
子供に聞かせられない?
髙橋さん) 息子が私に「ねえ、これって戦争のあと?」って聞いたの。そう言わざるを得ないすさまじい光景だった。でも「私も分からない」という感じでした。津波のことも、いまいちピンときていないし。
そこで逃げ出すこともできたんだけれども、よく見たら、遠くに私の実家が残っているのが見えたんですよね。本来だったら見えるはずがないんだけど、山際まで家が流されて無くなっていたから、見えたんですね。

髙橋さん) 母がよく「もし万が一、ここに津波がきたら、私お父さんを連れて2階に行くのが精いっぱいだ」って言っていたんです。それを聞いていたから、私が助けに行くのを待っているに違いないと思って、家の方に向かって行きました。
山際から匡美さんのご実家って、実際はかなり距離がありますよね。14日だと、まだ下の方は燃えていたと思うんですけど、瓦礫の山の中を歩いたんですね。
髙橋さん) そうですね。黒い柱とか焼けて、もう灰になる寸前のところにズボズボと足が入っていったりとか。砂と泥と油を含んだ黒い泥だから、普通のスニーカーでは足を取られちゃって、一回一回外して進みました。
途中で、ふと冷静になって、「息子は置いていった方がいいのかな」とも思ったんですが、ずっと何でも話してきた仲だし、何より、私が一人では怖かった。
でも、この話をすると、「うちの子供には聞かせられない」って言われるの。
そうなんですか。
髙橋さん) そういう時、今まではちょっと怒っていて。3.11の当時は、0歳からお年寄りまで全員、この状況を見て生きてきているんだよって。でも、そういう声を聞くと、やっぱり息子には見せてはいけなかったのかな、とちょっと思ってしまうこともあります。
話を聞きかれた方も、消化するのが難しいということがあるかもしれませんね。

髙橋さん) 自宅にたどり着いて、家中、父と母を探しました。はじめは見つけられなかったんですが、息子が「もう一回戻ろう」って言うので戻って探したら、亡くなった母を見つけました。
匡美さんが、大好きなお母さんの第一発見者になったのですね。
髙橋さん) まず、信じられないという気持ちですよね。病気で亡くなるのをどこかで看取るということは考えたことがあったけれど、こんな状態で見つかるなんて。でも、今考えると自分で見つけてあげられてよかったなと思います。
語り始めたきっかけ
匡美さんは、語り部をするときに、当時のことを細部までお話される印象があります。どんな思いがあるでしょうか?
髙橋さん) もともと「自分の話を聞いてほしかった」という気持ちがありました。当時は、もっと大変なことが渦巻いていて、私は石巻に住んいなかったし、「家もあるし家族も無事だったでしょ」と言われることもありました。「我慢するしかない」と思うけど、すごく辛くて、どうしたらいいのか、ずっと苦しんでいました。だから、誰かに聞いてほしかったんだと思います。
ご自身で、「聞いてほしかった」と気付かれたんですか?
髙橋さん) 最初は気付いていませんでした。「なんで私がこんな目に遭わなくてはならないんだ」という気持ちですね。ふつふつとした怒りでした。私は「悲しみ」よりも「怒り」の方が大きかったように思います。睡眠薬を飲んでは寝て、3年、ずっと自宅にこもっていました。今では、必要な時間だったと思いますけどね。
引きこもりの生活が変わったのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
髙橋さん) 2014年にTwitterでつながった“猫好きの会”で田代島に行くことになったのが、外に出るきっかけでした。その時、初めて他の人に、震災のときの話をしました。
そこからご自身の体験を話されるようになったんですね。
髙橋さん) はい。さらに、そこで一緒だった人の中に、被災した3県でのスピーチコンテストを企画していた人がいたんです。それに誘われたんですが、「もっと大変な人はたくさんいるから、私なんてとても」と断りました。「忘れよう、忘れよう」としていたことを思い出さなければならないのが嫌で。でも、その方がとても熱心で、石巻に来るたびに誘われて(笑)

髙橋さん) 最終的に、「匡美さんみたいに、実際家族を亡くしていなくても、鬱になって苦しんでいる人がたくさんいると思うの。そういう人たちに勇気を与えられるんじゃない?」という彼女の言葉を聞いて、それなら、と思ったんです。
熱い想いに動かされたんですね。
髙橋さん) さっそく「一泊二日の合宿があるから、それまでに原稿用意してください」と言われて、それまで書いていたブログを読み返す作業をしたんですが、全然、書けなくて。合宿も「調子悪いです」ってすぐ帰ろうと思っていたんだけど(笑)、「大丈夫ですよ。休み休みゆっくりやっていきましょうね」と言ってもらえたことでスイッチが入って、一気に27枚の原稿を書きました。それで、合宿では、スピーチの仕方や原稿の書き方など休みも無く本格的なレッスンを受けました。
休み無く(笑)
髙橋さん) 最初は「コンテスト」だから周りはライバルだと思っていたんだけど、参加してみたら、みんな、同じように辛い思いをした同志なんだって気付いたの。一泊した頃にはマジックにかかっていて(笑)、「このイベントをみんなで素敵なものにしよう!」という気持ちに変わっていました。
一気にやる気が高まったんですね。
髙橋さん) そう。2014年の11月に宮城県大会がありました。そこで、初めて人前で話して、マイクを持つ手もすごく震えるくらい緊張しました。
スピーチを終えて記録用のビデオカメラを向けられた時、正直に「ホッとした」と言いました。話すということは聞いてくれる人がいるということで、爽快感にも似た安心感に包まれました。
話すことで救われる
当時、匡美さんのお話を聞いていて、「解放された」とおっしゃっていたことがすごく印象的でした。私たちの団体でもちょうど「何のために伝承のプログラムを続けているのか」ということを話し合っていたタイミングだったのですが、話を聞きに来られる方のためはもちろん、話をする語り部さんにとっても意味があることなんだと気付くことができて、大きな転換点になったと思っています。
髙橋さん) 「苦しいことを話して大丈夫?」と言われるんですけれど、話すことで私自身が救われているんですよね。
私も、その話を聞いて「場」をつくることの価値に気付くことができました。

髙橋さん) 「私が話していいのか」という思いはあったんですが、依頼をいただけると「行っていいんだな」「行きたい」と思うようになりました。迷いはずっとありましたが、コロナになる少し前くらいに「私は話したいんだ」という一つの答えが出たような気がしました。そして手を挙げたからにはちゃんと話せるようになろうと。
匡美さんは、3年くらい前から英語での語り部にチャレンジされていますよね。英語で話す時と日本語で話す時、ご自身の中で変えていることはありますか?
髙橋さん) スピリットは変わりません。ただ、海外の方は、日本人と比べて、笑ったり、悲しそうな顔をするポイントがちょっと違うなと最近気付きました。

2018年7月、ニュージーランドの高校生受け入れの様子。
髙橋さん) 私の語りは、「あなたの故郷はどこですか?」という問いかけから始まります。どの言語圏の人でも、そこでは同じように、自分の家族を思い出してくれていると、最近はそう感じられるようになりました。
英語でも日本語でも、語るうえで大切にしているポイントはありますか?
髙橋さん) まずは、1回1回、丁寧に命がけで伝えるという自分の姿勢を変えたくないなと思っていて、相手が子供でも大人でも、全員同じように話をしています。
ただ、「自信もって話せた!」と思ったことは1度もないんです。でも、そのモヤモヤとした気持ちがあるうちは続けられる、「今日の語りは100点!」ってなった時がこの活動をやめる時なのかなと。もちろんいろんなスタイルがあって良いのですが、私としては、朗々と語ることはしたくないなと思っています。
仲間とつながり、伝え続ける
今年9月の修学旅行の受け入れで、久々に語り部さん7、8人が集まったときは同窓会みたいでしたよね。一人じゃないという雰囲気が印象的で、このつながりをどう広げていくかが大事だなと思いました。
髙橋さん) ゆるっとでもつながって、わいわい話しながらやっていけるといいですよね。
仲間と活動してる今、ご自身の中で変わったなと感じることはありますか?
髙橋さん) 去年くらいまでは、「震災後に出逢った全ての人や経験を捨てていいから、震災前に戻してほしい」と思っていました。でも、時が経過したからなのか、今年に入ってから「震災は過去の事なんだ」と受け止めることができるようになりました。新しいチャレンジや工夫もするようになって、車中案内のガイドもするようになりました。
南浜には、来年3月に復興祈念公園が開園して、たくさんの人が訪れると思います。改めて、匡美さんや語り部さんたちの活躍が期待されます。
髙橋さん) 楽しみですね。

匡美さんが考える「人とつながる意義・価値」は、どんなことでしょうか?
髙橋さん) 震災後、私が、苦しくて怒りに飲み込まれたのは、孤独だったからだと思います。思い切って扉を開けてみたら、手を差し伸べてくれる人がいっぱいいた。だから、元気な人は振り払われても何度でも差し伸べて、苦しい人はその手を見つけるためにとりあえず顔をあげてみてほしいと思います。一人でも生きていけると思っていたんですけれど、やっぱり一人では生きていけないし、やっぱり、人を助けられるのは人でしかない。無理する必要はないけれど、自分のペースでつながっていればいいのかなと思います。
本当にそうだと思います。
髙橋さん) 語り部の活動をする中で、かなり悩んだ時もありました。でも「いつでも辞められる」と腹をくくったら、「次、何しよう?」と考えられるようになりました。意志があれば、形を変えながらでも、伝えていけると思いますし、お互いにつながって、情報を共有しあうことで、チャンスが広がっていくと思います。
最後に、ネットワークの会員さんへのメッセージをお願いします。
髙橋さん) 語り部のときにもいつも言うことなのですが、伝承に取り組む皆さんにも。
明日が来るのは「奇跡」だから、「今」を生きていきましょう!
匡美さん、ありがとうございました!
インタビュー後記
インタビューは4回目。
「少しは慣れたかな?」と勝手に思っていましたが、5年以上のお付き合いがある方に改めてインタビューするのはお互いちょっと気恥ずかしく、長いインタビューとなってしまいました(汗)
最近、記憶があいまいになってきていますが、匡美さんと初めてお会いしたのは、2015年になってすぐの頃。
石巻市内の語り部さんから「紹介したい人がいる」と連絡をいただいたのがきっかけでした。
本文中に、スピーチコンテストで話した後、爽快感があったというお話がありました。
あの当時は、「デトックス」と表現されていましたが、それが私にとって“伝承”に対する考え方を変えたきっかけでした。
それまでは「そういう効果もあるのかな?」とは思うことはありましたが、はっきりと「話すことで、自分が救われた」とおっしゃる方にお会いしたのは初めてで、とても印象的な出会いでした。
そしてその後、沢山のことを経て今に至ります(笑)


※屋外で写真を撮る時のみマスクを外しています。
次回もお楽しみに!

インタビューアー / 藤間 千尋(ふじま ちひろ)
3.11メモリアルネットワーク 共同代表。
神奈川県横浜市出身で、3.11当時は海から約100mのみなとみらいの職場で仕事をしていた。
2011年のGWにボランティアで石巻市に来たことをきっかけに、同年10月に移住し、その後仕事で語り部プログラムの調整担当に。
趣味は読書、ドキュメンタリー映画やEテレの番組を観ること。