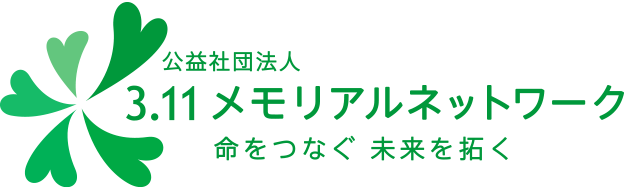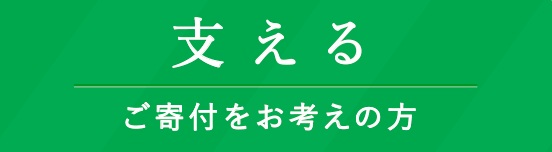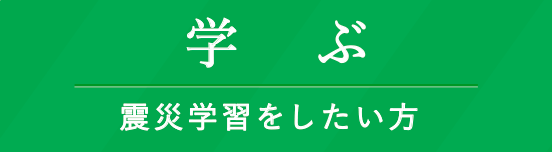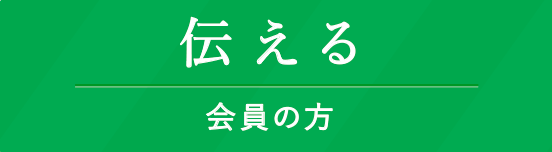3.11メモリアルネットワーク基金助成団体の紹介
3.11メモリアルネットワーク基金事務局の三浦です。
ブログ記事を書くのは初めてですが、2020年度に基金が設立されて以後、基金事務局として、助成採択された伝承団体の活動など聞かせていただいておりました。
基金の目的や、採択団体のみなさんの活動から見えてきたことなどご紹介します。
3.11メモリアルネットワーク基金は、東日本大震災を伝承する個人・団体・震災伝承拠点を結ぶ3.11メモリアルネットワークの目的に合致した活動を推進し、その継続を支えるための基金です。

2020年よりコロナ禍の緊急対応助成金も含めて6回公募し、延べ68事業に活用いただいています。これまでに申請いただいた申請額の合計は7,000万円を超えますが、事務局の力不足もあり、上限額(1,000万円)を設定させていただいており、すべての事業をお手伝いすることはできておりません。
伝承団体による伝承団体のための基金として、なるべく多くの事業をア後押しできるよう、採択された事業にもやむなく減額など条件をつけさせていただき極力不採択数を減らしているほか、貴重な基金寄付金は、これまで事務局経費を全くとらず、振込手数料以外は全額、助成団体に活用いただいています。
| 事業年度 | 採択数 | 採択金額(円) |
| 2020年度 | 13 | 9,916,000 |
| コロナ緊急 | 8 | 2,672,910 |
| 2021年度 | 12 | 9,982,900 |
| 2022年度 | 14 | 9,477,050 |
| 2023年度 | 10 | 9,966,261 |
| 2024年度 | 12 | 10,007,811 |
基金の事務局として、事業期間中必ず1度は、現場を訪問して活動の様子を見させていただいて、基金事業に関する質問や事業実施をする上での課題などを聞かせていただいています。
多くの事業を拝見して、一言で教訓といっても、場所や立場、人により得られる教訓が異なり、その教訓の伝え方も多様であることがわかりました。
津波からの避難行動、避難所の運営、原発避難など、教訓の前提となる事実が異なることはもちろん、当事者の年齢や性別、立場でも話しは変わります。また伝え方も、いわゆる語り部としての活動から、伝承アーカイブ、伝承施設の運営、フォーラムの開催や、絵本の作成、アートによる表現など様々です。
2024年度3.11メモリアルネットワーク基金採択団体は現在活動実施中ですので是非関心をお寄せいただければ幸いです。
過去5年の助成事業では、継続で採択された団体もあり、事業を重ねるごとの活動の進化、工夫は目を見張るものがあります。コロナ禍をきっかけにオンライン語り部を開始したところ、多言語による伝承活動にチャレンジしたところ、こども向けに絵本を作成したところなど、望まず、やむを得ず始めた伝承活動にも関わらず、東日本大震災と同じ犠牲を生み出さないという使命感で、活動を良くしようとみなさま必死に活動されています。
採択団体の中から、今回、2団体をご紹介します。
一般社団法人健太いのちの教室
1団体目は、一般社団法人健太いのちの教室田村ご夫妻です。
(写真提供:一般社団法人健太いのちの教室)


健太いのちの教室田村ご夫妻の息子さん、健太さんは発災時、七十七銀行女川支店にお勤めでした。
東日本大震災発災時、七十七銀行女川支店には13人の行員が働いていました。2階建ての屋上に避難するよう業務指示があり、結果12名の命が失われました。健太さんもそのお一人でした。歩いて数分の高台に逃げれば助かる命でした。
健太さんの捜索で女川に通い続ける日々の中、田村ご夫妻は女川を訪れた方々に、女川で起きた事実を伝えるようになり、伝承活動が始まりました。なぜ高台ではなく、屋上への避難指示だったのか。不条理なその犠牲を再び生むことが無い社会を目指し、特に組織管理下における命を守る災害安全対策に関する普及・啓発へと繋がります。
伝承活動を続ける中、お二人は、災害に限らず、事件や事故などにより多くの命が社会から失われていることを再認識されます。
失われた命の一つ一つに肉親や友人がいて、遺族となっています。活動を続ける中で、同じ犠牲を生むことがなくなるよう辛い経験を伝え、声を上げ続ける遺族の方々と知り合われます。そして、東日本大震災の枠を超え、様々な理由で肉親を失った遺族のみなさんと協力し、遺族が声を上げなくても命が失われない社会に向けて、社会へのメッセージを伝える「安全な社会を目指して」フォーラムを開催しました。遺族などの伝承者だけでなく、有識者や弁護士などの連帯による安全な社会づくりを目指しています。
一般社団法人大熊未来塾
2団体目は大熊未来塾木村さんです。
(写真提供:一般社団法人大熊未来塾)


大熊町で生まれ育った木村さんは、東日本大震災の津波で家族3人が行方不明となりますが、原発事故により捜索を打ち切って避難せざるをえない状況となりました。立ち入りが制限される帰還困難区域となった自宅周辺で、行方不明のままだった次女汐凪(ゆうな)さんの捜索を独自で続け、5年9か月後に遺骨の一部が発見されるものの、すべては見つかっていません。
大熊町の現状や自身が経験したことは、東京電力や国、その下で経済を優先し豊かに暮らす自分たちに対する警鐘と捉え、東日本大震災、原子力災害による教訓と、地域の伝統文化や記憶を継承することで、災害で命が失われない、持続可能で健全な社会を目指し、各地で講演、大熊町のスタディツアーを開催するなど、多くの人とともに考える機会を提供しています。
また、震災と原子力災害を経験した大熊町だからこそ、伝えられることがあると考え、大熊未来塾の仲間と共に、石巻や沖縄、広島、水俣を視察訪問し、そこで繋がったご縁をもとに、戦災や災害、公害などあらゆる犠牲を繰り返さないことを目指し、「伝承の仲間づくり」サミットを開催し100人を超える方が参加しました。大熊で何をのこし、何を伝えるのか、世代と地域と分野を超えた仲間たちと考えていらっしゃいます。
ご紹介したふたつの事例は、東日本大震災のみならず、震災の枠組みを超え改善すべき社会課題を連帯で訴えていらっしゃいます。東日本大震災の教訓が、防災に留まらず、すべての人々が社会を良くするために考えるきっかけとなることを体現してくれています。
今回、東日本大震災の伝承活動を支える3.11メモリアルネットワーク基金について、2つの事業にフォーカスを当てご紹介しました。3.11メモリアルネットワーク基金は、未来の命を救うという使命感と、伝承活動を支える善意からの寄付で成り立っている基金です。
12月11日には、伝承団体の交流会では、2団体からの報告をいただくほか、2025年度助成の説明会も開催させていただきます。
是非、東北の震災伝承活動を支える3.11メモリアルネットワーク基金へのご支援をいただければ幸いです。