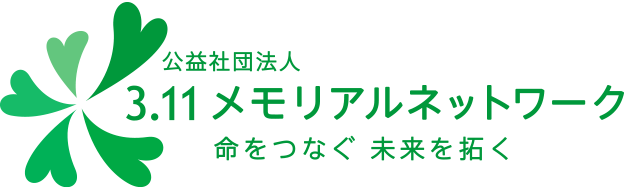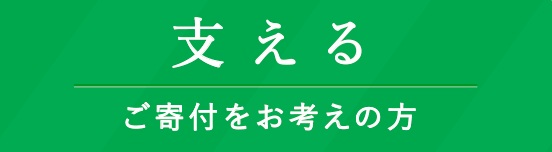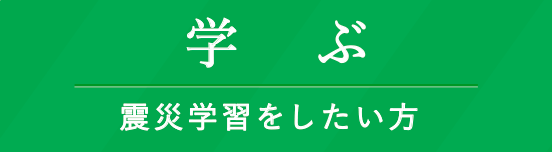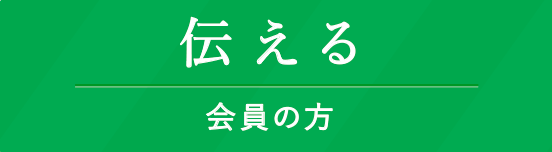【報告】第7回 東日本大震災伝承シンポジウム -継続の危機を越え、伝承の意義を未来へ- 開催
7回目となる今回のシンポジウムでは、震災伝承活動の意義を共有し、次世代への伝承を継続可能なものとするための事例共有とディスカッションを行いました。
震災から15年の節目に向け、継続性の不安を抱える被災地の伝承活動に対し、参加者全員でその意義を再度捉えなおし、未来の命を守る取り組みを持続可能なものとするために取り組むべき問題を考える場となりました。
折しも前々日の2月26日には、隣接する大船渡市大規模山林火災が発生。延焼が続く中で、開催会場や市の担当者に連絡し、交通事情やご負担等、現地にご迷惑にならないことを確認して開催させていただきました。


来賓ご挨拶
公益社団法人3.11メモリアルネットワーク代表理事・武田真一による開催挨拶に続いて、佐々木拓・陸前高田市長よりご挨拶をいただきました。

陸前高田市長 佐々木拓様
現在も大船渡市内の山林火災が続いております。被災された方々、避難された方々に心よりお見舞いを申し上げます。また、消火活動や被災者の支援活動に取り組んでいる皆さまに心から感謝を申し上げます。当市としてもしっかりと皆さまを支援してまいります。
東日本大震災から間もなく14年。未曽有の被害を受けた本市は国内外の皆さまのご支援をいただき、市民の皆さまが一体となって多くの困難を乗り越えて、復興に取り組んでまいりました。
本シンポジウムは、震災の記憶を風化させることなく、震災の記憶を共有し、防災・減災の取り組みを強化することで未来の災害に備えるよい機会です。陸前高田市としても、新たな防災や減災のアイデアや技術を学び、防災対策に活かしたいと思います。
私たちは震災の教訓を胸に刻み、未来に向けて力強く歩んでいく決意です。本日のシンポジウムが皆さまにとって有意義なものとなり、今後の防災・減災活動に役立つことを願い、ご挨拶とさせていただきます。
震災伝承調査結果報告・テーマ提起
議論に先立って、3.11メモリアルネットワーク専務理事・中川政治が、2024年度に実施した伝承調査の結果を報告し、震災伝承の継続の危機の現状について共有しました。
================
<伝承活動の現状>
震災学習プログラムと震災伝承施設の受入人数は、いずれも2024年に減少に転じました。
県別では、震災学習プログラムと震災伝承施設ともに、岩手県と宮城県では減っており、福島県だけが増えています。
こうした中、各伝承団体では活動の継続に大きな不安を抱いています。
調査した28の震災学習プログラム実施団体のうち、「全く不安のない」団体はゼロ。ほとんどの団体が、「伝承活動を継続する上で不安がある」と考えています。
伝承人材の確保については、3分の2の団体が「1年後の見通しも立っていない」と回答し、30年後も「見通しがついている」という団体はゼロでした。
================
<伝承の“崖”>
伝承活動の継続には、様々な困難があります。
まずは資金の問題。3.11メモリアルネットワークを例にとると、2025年度までは復興予算等による財源が付いていますが、その先は制度そのものが無くなってしまうため、ゼロになる可能性があります。
私はこれを、復興関連財源の“崖、”「災害伝承の“崖”」と呼び、危機感を抱いています。
伝承活動の継続にはこの他にも、「来訪者数の激減」「「語り手の逝去(宮城)」「民間団体の解散(宮城)」「民間施設の閉館」といった様々な「危機」があります。
震災から14年しか経っていないのに、伝承の力が失われてしまいつつあるかのようです。
================
<伝承活動の意義>
しかし、伝承活動には確かな力、意義があります。
語り部さんのお話を聞く前と聞いた後では8割の方が「自分の中で変わったことある」と答え、1年後の追跡調査でも7割の方が「自分の中で変わったことがある」と答えています。
また、語り部さんから聞いた話を自分の中だけに留めるのではなく、「家族にも話した」などの、行動変容も見られました。
「わかっていてもできない」が、防災対策の課題だと言われますが、このように震災伝承に」は「わかっていてもできない」を変える、確かな力があります。
================
<現状の課題>
1.災害伝承で巨大災害から多くの命を守ること
南海トラフ地震の津波死者は16万人と想定されています。
東日本大震災の教訓を活かせば、半数以上の9万人の命を救えます。
能登半島地震では「東日本大震災のことが頭にあって訓練をしていたから」逃げることができたという証言もあり、実際に多くの命を守りました。
2.若い世代を語り部として育成していくこと
岩手、宮城、福島の大学生が地元の語り部さんから学んで、修学旅行に来る生徒たちに伝える「次世代伝承サポーター」を、昨年から始めました。
3.語り部を「職業」として成り立たせること
アンケートでは「伝承を職業とすることが必要」という声が多くありました。
広島平和記念資料館は、政府・自治体による財政の裏付けもあって今も来場者数が増えています。
民が民を支える先進的な取り組み「3.11メモリアルネットワーク基金助成」の基金は、残り1.7年分と、危機的です。
ご協力をお願いします!
災害教訓継承のこれまでとこれから

復興庁(併)内閣府 参事官 後藤隆昭様
阪神淡路大震災から30年が過ぎました。
以来、神戸は、時代に対応しながら復興と防災に取り組み続けてきました。
神戸がこうして30年間続けてこられたのも、変化をしてきたからです。
神戸で語り部活動をしている方は、「やっぱり10年というのは一つの大きな節目だった」と言います。
最初の10年は、当時の大人だった世代が。10年後になると、今度は当時子供だった世代が。さらに20年経つと、震災を知らない世代の方々が、震災伝承活動を受け継いできました。。
今後の災害伝承は、「時間軸」「空間軸」「分野の広がり」の3つの視点で考えなければなりません。
風化や世代交代、社会の変化に対応すること。これが「時間軸」。
次に「空間軸」。東日本大震災の被災地同士や神戸とか他の被災地との繋がり・ネットワークが大切です。連携することで相乗効果があります。
そして「分野の広がり」。災害伝承単体ではなく、防災や地域振興、観光といかに繋がっていくかがポイントです。
そもそも、何のための災害伝承なでしょうか。
復興とか地域のアイデンティティーとか追悼とか、生きがいとか、いろいろありますが、やっぱり本質的には将来の災害を未然に防ぐことが一番大きいと思います。
復興庁の基本方針の中で、記憶と教訓を後世に伝承するという中で、その施設間で連携をして、災害伝承というものを位置づけており、防災力の向上というのが伝承の本来の意義ある目的なんだろう、というのが国の立場です。
防災基本計画の中でもこの災害教訓を防災につなげていくんだと言うのが、やはり国としての立場になっていきます。住民は自ら災害教訓の伝承に努めることが、災害対策基本計画では書かれています。国、地方公共団体がその啓発などでその支援していくんだというのが、基本的にはその行政のスタンスになっているということです。
防災庁は、今から1年半後に設置をされることになるかと思いますけれども、今、そこに向けた様々な準備を進めている段階ですけれども、その中でもその大きな論点になっているのが、その事前防災、あるいは防災教育ですね。
被災経験のない地域の方に防災を自分ごとと捉えていただくためには、実際に体験された方のお話を聞くことが大きなきっかけになります。
過去の教訓、過去の大きな被害を繰り返さないように、真剣に防災教育あるいは事前防災に取り組んでいく。その中にはしっかりとその災害教訓、災害伝承ということも位置付けていく方向で考えていく必要があると個人的には思っています。
これから「日本の防災の景色を変えていく」という意気込みで今進めています。防災をしっかりできるような環境をつくっていきたいというふうに考えています。
事例共有
伝承活動には様々なスタイルがあります。
岩手、宮城、福島で伝承活動に取り組んでいる方々から、活動の現状をご紹介いただきました。

(左から)小林大樹様、佐藤敏郎様、青木淑子様
================
一般社団法人陸前高田市観光物産協会
事務局長補佐 小林大樹様
パークガイドが始まったきっかけは、2019年9月の高田松原津波復興祈念公園一部オープンです。
「約130ヘクタールという非常に広大な公園。来訪者はどこを見てどこに行ったら良いかがわからないので、ガイドを実施してほしい」と陸前高田市から要請をいただき、新たに始めました。
ガイドは現在約30名で、うち10数名が実働しています。観光物産協会がガイド養成講習会と試験を実施して認定しています。2021年6月に観光物産協会の自主事業として運営を開始しました。ガイドの皆さんは陸前高田市にずっと住んでいた方々ばかりではなく、震災後にUターンした方やIターンで移住された方々も活躍しています。
パークガイドを始めてから今年1月末現在で約3年7か月になります。累計770件、団体さんや個人の方3万1688名をご案内しました。
ご利用者の8割以上が教育旅行で、その約半数が岩手県内の学校です。現在は、教育旅行の受け皿やコンテンツ提供者となる民泊や事業者との連携を深めているところです。
================
大川伝承の会
共同代表 佐藤敏郎様
震災について語ることは難しい。遺族が口を開けは「何か遺族が騒いでいる」という声が上がり、遺族ではない人が話せば「あなた、関係ないでしょう?」と。
大川小学校では今、大学生たちが語り部を始めています。彼らは仙台や関東の出身で、震災当時はまだ子どもでした。
「被災者でもない僕たちがここで語っていいのか?」というディスカッションを通り抜けて、語り部として立っています。
あの場所で遺族が話をすればインパクトはあります。でも、震災を体験していなくて聞き手と同じ立場の大学生が語る話を、同じ目線で聞くことができます。
大川小学校にはいろんな思い出が込められています。立場は色々でもみんなでしっかりと向き合って考え、立場を超えて話を聞いたり意見を交換したりしていくと、細い流れが大きな川になるんです。校歌の歌詞にもあるように、みんな未来に向かっているんです。
================
富岡町3・11を語る会
代表 青木淑子様
一人でも多くの方々に話を聞いていただく。聞いていただいた後に一緒に考える仲間になる。これが私たち「富岡町3・11を語る会」の伝承活動の最終目的です。講演、富岡の被災地や双葉町の伝承館でのガイド。これまでに延べ1万7507人の方々が話を聞いてくださいました。
なぜ語るの? 何を語るの? 私は何者なの? うちの「語り人」さんたちと心構えを常に確認し合っています。
なぜ語るのか? それは人の世に起きたことは人の言葉で語らなければならないと思うからです。人の言葉こそが大きな大きな心を伝えます。どんなに写真があろうと、データがあろうと、遺構があろうと、それは変わりません。
私たちは福島の複合災害、自然災害プラス原子力災害を語ります。語る私たちは身近な人の命を失い、居場所を失い、崩壊と創生の狭間で生きているのです。
14年経って、目に見えるものはますます少なくなっています。目に見えないものを、私たちはどれだけ言葉でちゃんと伝えることができるのか。今が語り人としての正念場です。
================
パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、震災伝承活動の意義、課題、展望の3つのテーマで意見交換していただきました。

【テーマ1 伝承活動の意義と価値】
(司会 武田代表理事)
伝承活動には次なる大災害に備える防災の視点からの意義と価値があります。
これについて、現場ではどんな手ごたえや気付きがあるでしょうか。
(佐藤)
私たちの話を聞いた先生が、学校に帰ってすぐに避難訓練をやり直したという事例があります。「今のままでは、うちの学校は子供たちを守れないということが分かった」と。能登の方でも、大川とか岩手県の話を聞いていたおかげで、子どもたちの目の色が変わったそうです。
(小林)
ツアーに参加したお客さまから「生徒たちが学校に戻ってから、実際にどう感じたかを話し合っていた」という話をいただくことがあります。
学校からのお礼のメッセージもよくいただきますが、感謝の言葉だけでなく、家の人と具体的な避難の方法について話し合ったという事例があったことも添えられていることが多いです。
(司会)
被災地や被災者自身にとって、伝承活動にはどんな価値がありますか?
(青木)
私は、原子力災害で失われた一番大きなものは人と人とのつながりだと思います。人による流言飛語やうわさなどで苦しめられ傷ついた心は、人の心によってしか癒すことができません。
原子力被害を受けた方々の苦しみや思いを、私たちが語ることで多くの人に知ってもらえる。知る人が一人でも増えれば、生きやすくなる人がいると思います。
そんな話を高校でお話したら、「僕は傷つける人じゃなくて、人を救う人になりたいと思いました」という感想をいただきました。「おお、高校生も捨てたもんじゃないな」と思いました。
(佐藤)
「語り部活動って人を救っているの?」と聞かれることがあります。でも、話をする当のおじいちゃんおばあちゃんは、「話をすることで自分の気持ちが整理されるとおっしゃっています。
(青木)
「体験も記憶もない私が、震災のことを話してもいいんですか?」と言っていた高校生たちも、「話していくことで、自分が自分を見つける」と言います。
(佐藤)
女川の被災地の子どもたちは一生懸命震災に向き合って、津波に強いまちづくりを提案したり、命の話をするようになりました。
(後藤)
神戸でも、高校生や中学生が30年前の震災を語り継いでいこうとしています。自分たちが語るのが本当に正しいのか、すごく悩みながら。
(司会)
なぜ伝承活動の意義と価値について質問をしたかというと、今、伝承活動に対する国や自治体の助成が次々となくなりつつあるからです。背景には、復興の意義を過小評価する考えがあるのではないかと思います。
小林さんにお聞きします。伝承活動、教育旅行の経済効果や交流効果について、実情はいかがでしょうか?
(小林)
陸前高田市のパークガイドの8割以上が教育旅行です。経済効果の具体的な数字は算出していませんが、交流効果は間違いなく生まれています。
市内には民泊にご協力をいただいている家庭が300近くありまして、そこの家で震災の話を聞いたり、生業を体験させていただいたりして、「また来たい」と帰っていく子もいます。実際に移住して生きた人もいます。繋がりという面でも効果は大きいと思います。
(青木)
福島でも、観光旅行に震災ツアーの要素を組み込む例が多いですね。
【テーマ2 今後の課題】
次は、震災伝承の今後の課題です。会場から「活動資金はどうやって確保していますか?」という質問がありましたが、いかがでしょうか?。
(青木)
福島県の場合は教育委員会が高校生の育成事業に乗り出しています。県外から来た学校が震災の話を聞きたいときには、費用を県が肩代わりして無料で提供しています。
(佐藤)
大川の場合は、おっちゃんおばちゃんが仕事の合間に語っているだけ。お金のかかることは特に何もしていないので、現状では資金に困っているということはありません。
しかし、今後、きちっとした活動にしていくためにはお金の確保も必要になるでしょうね。
(小林)
パークガイドは発足以来、お客様からきちんとガイド料をいただいて活動資金を確保しています。教育旅行については2、3年先まで受入人数の見通しが立っており、今のところは経済的に危機的な状況というわけではありません。
(後藤)
行政がどこまでこうした伝承活動を金銭的に支援するのか、非常に難しいところがあります。内閣府でボランティアを担当していますが、どこまで支援すべきかには議論があって、結論は出ていません。
また、語り部活動が行政からお金を受け取ると、行政批判がしづらくなるのでは、という懸念もあります。
とは言え、将来防災庁が発足した際には、事前防災や防災教育が重要となると考えています。
【テーマ3 展望】
(司会)
最後に、これからどんな方向に進むべきか、展望をお願いします。
(青木)
活動を継続するためには、経済的な支えは絶対に必要です。私は、あくまでも行政が伝承活動を支えていくべきであると思います。支える手は、絶対に抜かないでいただきたい。
富岡町では「町民皆語り部」という取り組みを始めました。皆さんの震災の体験や記憶には、まだ表に出ずに埋もれているものが山のようにあります。それらが、14年経ってもまだまだ全然掘り起こされていません。もっともっと、聞き出して、語ってもらわなければなりません。伝承活動の継続と、そのための支援が必要なのです。
(佐藤)
最大の作戦は、諦めないこと。私は絶対に諦めないで、ドアを叩き続け、種をまき続けます。
(青木)
むしろ大事なのはこれから。震災を知らない世代に伝承活動を引き継がなければなりません。
(小林)
自分たちが発信をし続けることでお客さまが訪れる。それがやがて国や行政を動かして、東北に、岩手宮城福島に、もっと多くの方々が来ていただけるような取り組みを、行政には強化していただきたいです。
物価高騰のために教育旅行のコースの範囲が狭まっています。移動に助成していただければ効果があると思います。例えば福島では、教育旅行にバス代を助成するなど、先進的な取り組みがありますよね。
(後藤)
今日は大変重い宿題をいただきました。国が簡単に予算を付けられるというものではありませんが、皆さんの伝承活動、情報発信が国民的な合意に届くことが、実現のためには大事になると思います。
================
◆◆◆参加者からの質問への回答◆◆◆
Q.1
「原子力を批判してはならない」と行政などから言われることはないのですか?
(青木)
福島県は今から3年前に、生涯学習課が音頭をとって福島県内で語り部活動を行っている団体や個人を集め、「語り部ネットワーク会議」を作ってくれました。ずっと要望していたことだったので、すごく嬉しかったです。
ただ、立ち上げの際に、一つ確認しました。「語り部は、自分自身が語りたいことを話す」。たとえ県から「こん風な話をしてください」みたいなことを言われても、意に沿わなければ、語り部さんは絶対に断ります。例えば「福島県は明るい未来に向かって進んでいます」とは、言えと言われても言わない。進んでいるところもあれば進んでいないところもあるから。語り部さんそれぞれが思うことを言うことにしています。
ちなみに、とある新聞が「語り部は原子力の東京電力に対して批判をしてはいけないと県に言われている」と書き立てたことがあります。しかし、これは事実ではありません。
Q.2
震災を経験していない子どもたちに一番伝えたいことは?
(青木)
震災が記憶にない、体験していないということは伝承活動には何らマイナスにはなりません。まずそこから始めています。私自身も双葉郡の人間ではありません。逆にそれがとても大きな強みになっているのかもしれません。
Q.3
パークガイドさんは何人いるんですか? 応募方法は?
(私もパークガイドになりたいんです)
(小林)
観光物産協会認定のガイドは30名ですが、専業のガイドではなくて、それぞれの本業があります。私自身も物産協会で働きながら皆さんと一緒に試験を受けてガイドになり、活動しています。
募集は観光物産協会のホームページとかで告知をしています。応募の条件は特にありません。
ガイドとして活動する思いを持っている方、自身の言葉で伝えられる方と、ぜひ一緒にやっていきたいと思っています。
Q.4
どのような勉強が必要ですか?
(小林)
「震災前の陸前高田のことなんか何も知らない」というガイドもたくさんいらっしゃいます。移住者や、震災後にUターンした方、震災直前の様子も震災当初の様子もわからない。そういった方々でもなれるように、広く陸前高田の地域産業や観光業などを勉強して、陸前高田の知識をつけていただいています。
Q.5
語り部を行う際に、何か表現の工夫や言葉の吟味をしていますか?
(佐藤)
丁寧な言葉で語ること。説明の内容は中学生レベルを基準にすると、小学生にも大人にも伝わりやすいです。
それと、どんな方が聞き手なのかを意識して、相手の立場に合わせて話します。私自身が元教員なので、例えば学校の先生には学校の仕組みみたいなことも絡めて話します。また、母親の人たちにはお母さんの気持ちに寄せて話をします。
================
東日本大震災伝承シンポジウム宣言
このシンポジウムの議論を踏まえ、東日本をはじめあらゆる災害の伝承活動の維持発展に取り組む決意を共有するために、「東日本大震災伝承シンポジウム宣言」を参加者全員の拍手によって採択しました。
================================
東日本大震災伝承シンポジウム
「宣言」
わたしたちは、本日のシンポジウムの議論を踏まえ、以下の通り、東日本大震災をはじめ、あらゆる災害の伝承活動の維持・発展に取り組む決意を共有します
1.【災害犠牲を繰り返さない】
災害からいのちを守り、被災地域が再生に向かえる社会の実現に向け、防災意識や行動変容を導く伝承活動の成果を手に、人から人へ伝え継ぐ輪を広げていきます
2.【伝承の多様な意義を確かめ合う】
被災地・被災者自身が経験に向き合って、来訪者とともに未来を拓く一歩を重ねている意義を確かめ合い、いのちや人権等の普遍的価値観の共有、交流による地域振興の効果等も含め、災害伝承の多様な価値と役割を発信し続けます
3.【つながり合って持続的な基盤を未来へ】
後継人材の育成や活動資金等の課題を直視し、自助努力を重ねながら必要な支援や施策に訴え、世代や地域を越えたネットワークの力によって持続的な震災・災害伝承の基盤づくりに取り組みます
2025年3月1日 東日本大震災伝承シンポジウム 参加者一同
公益社団法人3.11メモリアルネットワーク
=====
◆◆◆アンケートより◆◆◆
参加した方々からは、たくさんの貴重なご意見と感想をいただきました。
- 伝承活動の課題が共有できた。
- 様々な地域で行われている伝承活動を知ることができたということが、とても良かった。
- 被災者でなくても語ること、語りを通して語る側も成長できるということが印象的でした。
- 小さな語り継ぎを1人でやっていて挫けるときもありますが、継続させていこうと思いました
- 人々の気持ちはまだ全然語りつくされていない。それを掘り起こすことが伝承と思います
こうした声を励みに、これからも皆さまとともに震災伝承活動の継続と発展に尽力してまいります。
本事業は「2024年度日本郵便年賀寄付金助成事業」からの助成をいただき開催しました。